「小児がん患者・経験者自立支援プログラムの整備」報告 2.小児がん患者・経験者自立支援における学校教育の役割~病弱教育との関連から~
HOME > はばたきインフォメーションスクエア > 研究・その他医療情報 > 研究・成果
- 2012.4. 2
小児がん患者・経験者自立支援における学校教育の役割 ~病弱教育との関連から~
西牧 謙吾氏(独立行政法人国立特別支援教育総合研究所)
学齢期の子どもが小児がんを発症した場合、小児がんの専門病院に入院し、初期治療が成功し、生命の危機を脱したころから、子どもも親も学校教育が気になり始めることが多い。現行の学校教育制度下では在籍する小中学校からは、訪問教育を行えないので、病院にある学校に学籍を移動して(本人からみれば転校して)、特別支援教育を受けることになる。特別支援教育の中で、特に病気の子どもの教育を病弱教育と呼ぶことになっている。つまり、入院中の小児がんのある子どもは、病弱教育を受けることになる。
例えば、小児白血病研究会QOL小委員会が行ったアンケート調査に参加した研究参加施設1)に登録された、小児がんのある子どもが入院する病院には、いわゆる院内学級と呼ばれる教室もあるが、実際は特別支援学校やその分校、分教室、または訪問教育で学校教育が行われているか、学校教育が保障されていないところもある。いわゆる院内学級とは、正式には小中学校の病弱身体虚弱特別支援学級が、学校内ではなく病院内に設置されている場合の別称であり、法律用語としては存在しない。小中学校の学校外教室なので、高等部(高等学校)の教室は設置できない。つまり、高校生は通えないことになる。また、特別支援学校から訪問教育まで、病院における学校の設置形態により、教員の配置や教材教具を含む施設設備のレベルが違う。学校の方が、教員の配置や設備が手厚い2)。
1)JACLSQOL小委員会,小児急性リンパ芽球性白血病患児・家族のQOLアンケート調査―第1報,日本小児科学会誌115巻5号,918~930,2011.
2)滝川国芳,西牧謙吾,病院にある学校のあり方と病気による長期欠席者への対応,課題別研究「我が国の病気のある子どもの教育の在り方に関する研究―病弱教育と学校保健の連携を視野に入れてー」報告書,国立特別支援教育総合研究所;2008.p.24~36.
しかし、医療関係者から見れば、小児がんの子どもを見てくれる教員と学校という理解にとどまり、入院中の小児がんのある子どものQOL向上を議論するとき、教育における学校種の差に注目した議論は余り見かけない。
最近、がん対策基本法に基づく第2次がん対策推進基本計画に、小児がんを分野別施策に追加することが盛り込まれた。第1次計画では小児がんに対する施策は無く、そのために小児がん患者や家族と小児がん診療に携わる人々は、ほとんど恩恵を受けられなかった。その理由として、大学病院と一部のがんセンターを除けば、がん診療拠点病院のほとんどは小児がんの診療をしていないこと、小児がん患者の大半を実際に診療している小児医療専門施設(こども病院など)は、制度的にがん診療拠点病院の要件を満たすのが難しいこと、また、地域がん登録は、既存の小児がん登録である学会独自の登録制度か小児慢性特定疾患治療研究事業とはリンクしていないことがあげられる。
そこで、小児がん対策として、小児がん拠点病院の指定し、質の高い医療体制を構築し、緩和ケアの推進、小児がん患者への相談支援や療養環境の向上のためにプレイルームの運営等に必要な経費の財政的支援を行うとされたが、実際に小児がんを拠点病院として整備される病院の建て替え時に学校がなくなるケースも出てきており、検討段階でもう少し学校教育や生活支援を含めた包括的な議論があってしかるべきであった。
入院中の療養環境の整備や入院生活の質の向上や病棟での質の向上には、チャイルドライフスペシャリスト配置の拡充やプレイルームの充実も重要であるが、教育施設の観点からの整備も見逃せない。ここでは、小児がん患者・経験者自立支援における学校教育の役割について述べる。
小児慢性特定疾患治療研究事業には、悪性新生物で12,802人(平成20年度)が登録されており、年間2000人ほどの小児がん新規登録(正確には悪性新生物を意味する)がある3)。これは18歳未満の子どものおおよそ千人に1人が小児がんのある子どもと言うことになる。
3)松井陽(研究代表者).厚生労働科学研究費助成成育疾患克服等次世代育成基盤事業「小児慢性疾患の登録・管理・解析・情報提供に関する研究」平成22年度 総括分担研究報告書、2011.3
近年、小児がんの治療は、化学療法、放射線療法、外科療法などのあらゆる治療方式を駆使した集学的治療が行われ、一部の白血病のように、期待される生存率が80%を超える疾患も出てきた。その結果、治療後長期間を経てみられる遅発性の影響(late effects)を考慮する必要が出てきた。特に近年では抗がん剤や放射線照射による中枢神経系への影響により、認知機能の障害が知られるようになった。認知機能は日常生活の質を決定づける重要な能力のひとつであり、小児がんの治療において、生存率と生活の質(quality of life)のバランスを考慮する上での判断材料になり得ると考えられる4)。
4)船木聡美,小児がんの子どもたちへの教育支援システムの構築,小児保健研究 Vol.70 No.4,467~471,2011.日本子ども家庭総合研究所,日本子ども資料年鑑2010,KTC中央出版;2010.
特別支援教育の大きな成果の一つとして、発達障害のある子どもの教育支援が進んだことがあげられる。しかし、同じ認知機能に障害が見られる小児がんのある子どもの教育支援の必要性は、学校関係者にほとんど認知すらされていない。例えば,日本では、平成20年度に病気を理由に年間30日以上欠席した小学生は24,291人,中学生は20,826人であった。この数は減少傾向にはなく,平成20年5月1日現在の全国の特別支援学校の在学者数が,小学部35,256人,中学部27,046人であることと比較すると,病気を理由に長期欠席している児童生徒数の多さが改めて認識される。
ここで,理解の正確を期すために,病気を理由に長期欠席している児童生徒は,不登校で長期欠席している,小学校22,703人,中学校104,135人とは区別して集計されていることを強調しておきたい5)。復学支援がうまくいかず、不幸にも不登校状態に陥る小児がんのある子どもは、後を絶たない。病気のあるという理由だけで、発達障害と同じ方法で支援できる認知機能障害のある小児がんの子どもの学校教育が保障されないことが、今でも起こっているのである。
5)特別支援教育資料(平成21年度),文部科学省初等中等教育局特別支援教育課;平成22年4月.
 3.特別支援教育に用意された障害や病気のある子どもを支える仕組み
3.特別支援教育に用意された障害や病気のある子どもを支える仕組み
平成18年の学校教育法改正により、平成19年4月より、特別支援教育を推進するために,学校現場に新しくいくつかの仕組みが用意された。
一つは,特別支援学校の活用である。平成21年5月1日現在,全国に特別支援学校1,030校と教員85,400人,特別支援学級42,067学級と教員45,001人がおり,彼らの特別支援教育教諭等免許状の保有率は,特別支援学校69.5%,特別支援学級31.6%であった5)。このような教員の専門性を,地域の障害や病気のある子どもを支える社会資源として活用するために,学校教育法で,特別支援学校のセンター的機能(要請に応じて必要な助言または援助を行うよう努める)が規定された。特別支援学校は,複数の障害種に対応できる総合的な学校になり,重複障害にも対応出来るようになった。また,校長により指名された特別支援学校の特別支援教育コーディネーターは,小中学校等からの教育相談を通じて,または地域の福祉・医療等の関係機関との間の連絡調整役として,地域の特別支援教育推進の中核を担うことが求められた。教育との連携の窓口として,特別支援教育コーディネーターは重要なパートナーである。
関係機関が教育と連携を進めるツールとしては,個別の教育支援計画が重要である。これは,乳幼児期から学校卒業後までの長期的な視点に立って,医療,保健,福祉,教育,労働等の関係機関が連携して,障害のある子ども一人一人のニーズに対応した支援を効果的に実施するための計画と説明される5)。言い換えれば,障害のある子どものニーズ,支援の目標や内容,支援を行う者や機関の役割分担,支援の内容や効果の評価方法を関係機関の合意にもと書き込まれた「覚え書き」である。現行の学習指導要領では,障害や病気があれば必ず作成することになっており,医療者は,学校生活における配慮事項がある場合に活用していただきたい。
学校現場では,医療情報は保護者を通じて得られる場合が多く,更新されても不正確で断片的なことが多いことには注意が必要である。また,教員側も,観察力の高い教員では,学校現場にある有用な医療情報を得てはいるが,その情報発進力が弱く,医療には届き難い。個別の教育支援計画作成は,医教連携の進めるためのON THE JOB TRAININGの機会なのである。
5)特別支援教育資料(平成21年度),文部科学省初等中等教育局特別支援教育課;平成22年4月.
 4.病気のある子どもの教育についての啓発
4.病気のある子どもの教育についての啓発
~支援冊子「病気の子どもの理解のために」~
小児がんのある子どもの復学支援を進めるには、小中学校現場に病弱教育という仕組みを広く理解してもらう必要がある。病気による長期欠席者という教育支援が届かない隙間が生じた理由は,元々学校教育は学校に来ない子どもへの指導には弱い点と病気であればまず病気をことが先決であるという一般的な考え方があるからである。退院後前籍校に復帰する時に不登校に陥ることを予防するために特別支援教育に用意された個別の教育支援計画も十分に活用されているとは言い難い。そこで,国立特別支援教育総合研究所と全国特別支援学校病弱教育校長会と共同で,支援冊子「病気の子どもの理解のために」を作成し,特別支援学校(病弱)のセンター的機能を利用して,小中学校に在籍する病気の子ども理解啓発に努めている7)。
7)病気の児童生徒への特別支援教育支援冊子 病気の子どもの理解のために
http://www.nise.go.jp/portal/elearn/shiryou/byoujyaku/supportbooklet.html
これは,医療の専門家や病気のある子どもの親の会のスーパーバイズを受け,病弱の特別支援学校教員が小中学校等の教員のために作成したものである。どの検索エンジンでも、支援冊子で検索すれば,トップに表示され、誰でも利用可能である。現在、身体疾患、精神疾患に関する総論、白血病、脳腫瘍、アレルギーや心臓病、腎臓病、肥満、てんかんの他に、筋ジストロフィー、胆道閉鎖症、色素性乾皮症などの希少疾患など、14疾患の冊子を作成している。
1990年頃より高齢社会の到来を目前にして、寝たきりを予防する地域の仕組みとして、「地域包括ケアシステム」という概念が提案された。高齢者医療抑制と保健予防活動と高齢者福祉を包括的に捉え、地域住民に対し、保健サービス(健康づくり)、医療サービス及び在宅ケア、リハビリテーション等の介護を含む福祉サービスを、関係者が連携、協力して、地域住民のニーズに応じて一体的、体系的に提供する仕組みと説明されている。ソフト面では、その地域にある保健・医療・介護・福祉の関係者が連携してサービスを提供するものであり、ハード面では、そのために必要な施設が整備され、地域の保健・医療・介護・福祉の資源が連携、統合されて運営される。この地域包括ケアシステムを社会理論の見地から理論化した研究が出てきた8)。猪飼8)によれば、現在生じている健康概念の転換が、「医学モデル」から「生活モデル」への転換として生じていることを踏まえ、第1 に、健康概念の転換に適合的なヘルスケアは、より包括的かつ地域的であるという意味において地域包括ケアシステムを指向すること、第2 に、健康概念の転換が、過去30 年間にわたり社会福祉に広範に生じている生活支援の作法の転換を背景としていると考えられること、第3に、地域包括ケアシステムの構築に際しては、従来のヘルスケアとは質的に異なる、専門職の分業、社会関係資本の構築、コスト増大への対応等に関する課題の解決が必要になることを指摘している。
この考え方は、少子化社会において、障害や病気のある子どもの子育て支援にも、そのまま当てはまると考える。上記の小児がん対策をこの視点から眺めれば、未だ医療モデルの考え方を踏襲しているといわざるを得ず、時代の流れからは生活モデルの視点を導入し、教育も視野に入れたものにしていく必要がある。
前述の支援冊子プロジェクトは、病弱の特別支援学校の個々の教員の経験知を、テレビ会議システムと情報を集積するコンテンツ・マネージメント・システムのICT(Information and Communication Technology)を活用し、教員の学校業務の範囲内で全国の専門性の高い教員が分業で、交通費や執筆謝金などのコストをほとんどかけずに作成している。教育システムの活用を視野に入れれば、チャイルドライフスペシャリストの機能を補完する病院内幼稚園という発想も出てくる。これは、学校教育の財源で制度的には整備可能である。
小児がんの地域包括支援体制の構築には、小児がん拠点病院における質の高い医療の提供や療養環境の整備だけでなく、子どもが育つ環境の一つである学校教育と生活支援の視点を重層して考える必要があると考える。
子どもが,長期欠席、学校不適応,非行,落ちこぼれに陥っている場合、子どもの中にある障害や病気などの生きにくさそのものにその原因があるのではなく,問題を抱える子どもや家族の背後に存在する家庭的,社会的、経済的問題に起因することが多い。それらの多くは,医療や教育の中だけでは解決は不可能で、生活を支える視点が不可欠になる。しかし現実は,教育は教育,医療は医療,福祉は福祉で別々に支援し,関係機関の間で情報がうまく流れておらず,その支援は非効率的で効果も薄い場合が多い。残念ながら,学校現場では,個別の教育支援計画を作成しても,個人情報保護という名目で,適切な医療情報は保護者を通じて学校に伝わっておらず,学校生活の様子も,医療機関にフィードバックされていない事例がよく見られる。つまり,障害や病気のある子どもの情報が,関係者にうまく共有出来ていないことから来る非効率がある。
小児がんの地域包括支援体制の構築の前提として、小児がんに関わる支援者の誰かが、うまく情報を回す役回りを演じる必要がある。小児がんのある子どもの個別の教育支援計画が地域で数多く作られれば作られるほど,今まで地域に蓄積されてきた様々な社会資源のネットワーク化が進み,地域で生活する障害のある人が生活しやすい仕組みが出来上がる。その過程で,地域における地域包括支援体制の構築も進むと考えられる。
6)小中学校におけるLD(学習障害),ADHD(注意欠陥/多動性障害),高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のためのガイドライン(試案),文部科学省;平成16年1月.
8)猪飼周平,病院の世紀の理論,有斐閣.2010.

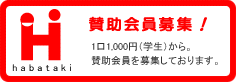
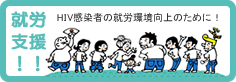


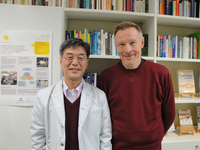


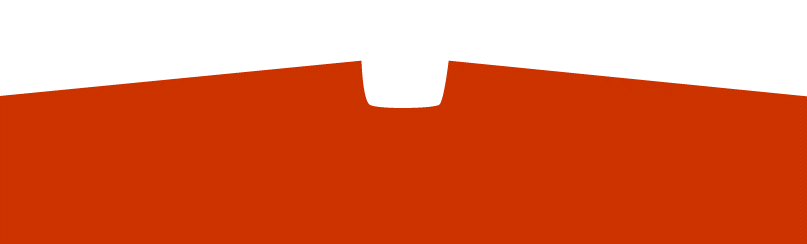

 お問い合わせ
お問い合わせ